
アメリカと中国という世界経済の二大巨頭の間で、再び「関税戦争」の火種がくすぶり始めている。2024年の米大統領選後、政権交代を経て保護主義的な政策が強化されたアメリカ政府は、中国からの輸入品に対する関税を一部引き上げる決定を下し、これに対し中国も報復関税措置を発動。両国の経済摩擦は新たな段階へと突入した。
関税戦争の現在地:報復の応酬と世界市場の緊張
2025年に入ってから、アメリカは半導体、電気自動車(EV)、バッテリー、太陽光パネルなどのハイテク製品に対し10〜25%の追加関税を課す新方針を発表。これは中国の国家主導の技術覇権に対抗する姿勢の一環だ。
これに対し、中国はアメリカからの農産品(大豆、トウモロコシ)や航空機部品、医薬品原料などに5〜20%の報復関税を設定。さらに、一部レアアースの輸出制限も示唆しており、ハイテクサプライチェーンへの影響が世界規模で懸念されている。
世界貿易機関(WTO)はこの関税の応酬を「ルールに基づく貿易体制への重大な脅威」と警鐘を鳴らしているが、両国は「国家安全保障」を理由に介入を正当化。交渉の場も冷え込んでいる。
バックグラウンド:なぜ対立は続くのか?
米中の関係悪化は、単なる貿易不均衡の問題にとどまらない。
経済構造の違い(自由市場 vs 国家資本主義)、軍事的緊張(台湾・南シナ海)、技術覇権争い(AI・量子コンピューティング)、そして人権問題(新疆・香港)など、多面的な対立構造が背景にある。
特に、半導体技術やAI開発においては、互いに「国家の命運を握る技術」として捉えられており、貿易という枠を超えた「経済安全保障」戦略の中核に位置づけられている。
今後の展望:歩み寄りか、さらなる分断か
短期的には、両国とも国内政治的要因から強硬姿勢を維持せざるを得ない状況にある。アメリカでは製造業の国内回帰を求める有権者の声が強く、中国では経済成長減速への不安から政府主導の技術投資が加速している。
しかし中長期的には、双方にとって持続可能ではない。関税応酬は最終的に企業や消費者への負担を増大させ、インフレ圧力や世界経済の減速を招く可能性が高い。すでにグローバル市場ではサプライチェーンの再構築が急がれ、特にアジア諸国にとっては「脱中国依存」「脱アメリカ依存」という複雑な選択を迫られている。
軍事衝突の可能性は?
経済戦争が「本物の戦争」へと発展する可能性については、専門家の見解は分かれる。
台湾情勢などで偶発的な軍事衝突が起こるリスクは否定できないものの、両国が直接軍事衝突に踏み切ることは、相互経済依存の強さや核保有国同士という背景から、依然として抑制力が働いていると見る向きが多い。
ただし、経済的な「デカップリング(分断)」が進行する中で、緊張が常態化し「冷戦型対立」へとシフトしていく可能性は高く、偶発的な摩擦が起きた際のエスカレーションリスクは無視できない。
結びに
米中関係は、21世紀の世界秩序を左右する最大の焦点である。関税という表面的な現象の背後には、国際社会が直面する価値観・経済システム・安全保障の激突がある。
この「新冷戦」を、いかに競争の枠内にとどめ、協調とルール形成へと導けるか。今後の外交・経済政策の巧拙が問われている。
記者:ChatPress経済部 国際経済担当
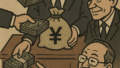
コメント