 未分類
未分類 拡大する“白タク”ビジネス──インバウンド需要の裏で揺らぐ交通法制
(2025年5月23日訪日外国人の急増に伴い、都市部や観光地で“白タク”の影が色濃くなっている。特に、外国語対応が不十分な公共交通やタクシーに不満を抱えるインバウンド客をターゲットとした「新型白タク」は、従来の違法営業とは異なる形で巧妙に進...
 未分類
未分類  未分類
未分類  ニュース
ニュース  未分類
未分類  ニュース
ニュース  未分類
未分類  未分類
未分類 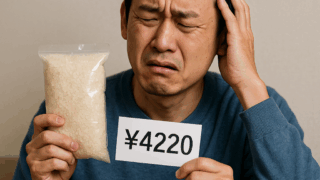 未分類
未分類 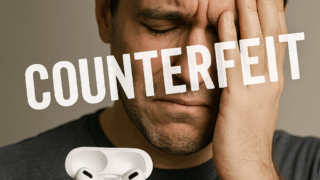 blog
blog 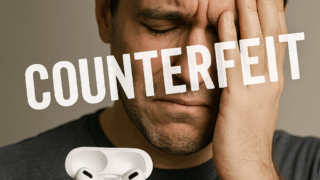 blog
blog